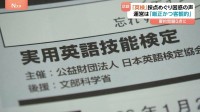シニア犬が罹りやすい病気|症状や対策法を、犬の性別・大きさ別に獣医が解説
犬は小型犬なら10歳、大型犬なら8歳くらいから、ちょっと年をとったかなと思えることが増えてくるようです。今回はシニア犬によくみられる病気を解説していきます。
犬の性別

人も男性と女性ではかかりやすい病気も違ってきますね。
犬も同じです。
ただし、犬は避妊、去勢手術が施されていることも多いです。
その場合には性ホルモンの影響による病気のリスクは大幅に軽減されることになります。
したがって、性別によるかかりやすい病気といった場合の性別とは、避妊、去勢手術をしていない犬のことをいいます。
去勢していないオスがかかりやすい病気

肛門周囲腺腫
犬がおしりをやたらと舐めていたり、便に真っ赤な鮮血がついていたりしたら、肛門周りを軽く触ってみてください。
豆粒大のできものが見つかるかもしれません。
肛門周囲腺腫の原因には男性ホルモンが関わっていると考えられています。
そのため、この疾患にかかる犬のほとんどが未去勢のオス犬です。
治療は外科的に切除することになります。
再発予防のため、去勢手術も同時に行われることが多いです。
腫瘍が小さいうちに取ったほうが治りも早いので、肛門周りにできものを発見したら早めに動物病院につれていくようにしてください。
会陰ヘルニア
肛門周辺の会陰部といわれる部分の筋肉が萎縮したり、緩くなったりすることでその隙間から膀胱や直腸などの臓器が飛び出してしまう病気です。
筋肉がやせてくる原因の一つに男性ホルモンの影響が考えられており、未去勢のシニア犬にしばしばみられる疾患となっています。
会陰ヘルニアをわずらった犬は、まず「しぶり」の症状を示すようになります。
便が出づらいために犬は何度も排便姿勢を繰り返します。
ほっておくと便がでなくなることもあり、肛門周辺が便でふくらんできます。
この段階になると多くの飼い主さんは動物病院を受診されます。
この病気で注意しないといけないのは、筋肉の隙間に膀胱が飛び出してしまったときです。
その場合は尿が出なくなってしまうことがあるのです。
排尿できなくなると、短時間のうちに腎不全となってしまいます。
そうなると、命に関わってきます。
便が出づらい程度のうちは手術に耐える体力もあるので、その段階で処置を施したほうがいいです。
犬が排便困難でいきんでいたら、早めに動物病院につれていってください。
前立腺肥大症
前立腺が肥大する原因には男性ホルモンが深く関わっていると考えられています。
そのため、この疾患は去勢していないオスにみられます。
前立腺が肥大していても特になんの症状もなければ治療はおこなわれません。
前立腺が肥大することにより、直腸が圧迫され便がスムーズにでなくなったり、尿道が圧迫されて排尿困難になった場合には去勢手術などの治療が行われます。
避妊していないメス犬がかかりやすい病気

子宮蓄膿症
子宮蓄膿症は細菌感染により子宮が炎症をおこし、内部に膿が溜まってしまう病気です。
以前は、高齢のメス犬はこの病気で来院することが多かったのですが、、最近は避妊手術をしている犬が多くなり、昔よりはずいぶんと減った印象です。
子宮の病気ですので、避妊手術がしてある犬は100%かかることはありません。
雌犬は発情中、子宮内において細菌感染を起こしやすくなっています。
とくに、高齢になり免疫力が落ちてくると細菌への抵抗力も弱くなってしまいます。
そのため、この疾患は発情出血がみられた1~2ヶ月後にかかることが多いです。
大事なことはこの病気が子宮だけの病気ではないということです。
子宮内の細菌が毒素を放出することにより、犬がショック状態(エンドトキシンショック)になってしまうことがあります。
こうなると犬は腎機能が低下し、危険な状態に陥ります。
子宮蓄膿症治療の第一選択は卵巣、子宮摘出術です。しかし、犬の状態によっては手術のリスクが高くなってしまうこともあります。
犬が食欲もあって、まだ余力のある段階で行ったほうが経過は良好です。そのためには早期発見が重要になります。
以下のような症状が認められたら、はやめに獣医師に相談してください。
- 陰部から膿のようなものがでている。
- 陰部が膨らんでいる
- 食欲は減ったが、水はたくさん飲むようになった。
- 嘔吐する
- お腹が張っている感じがする
また、今までも発情中は少し元気がなくなったり、食欲が落ちることがあった犬は特に注意しておいたほうがいいと思います。
乳腺腫瘍
犬の乳腺腫瘍の発生には女性ホルモンが深くかかわっていると考えられています。
そのため、若いうちに避妊手術を行うことで乳腺腫瘍の発生をかなり防ぐことができます。
特に初回発情前に避妊手術で卵巣を摘出した犬では、将来乳腺腫瘍にかかる確率は0.5%となっています。
乳腺に腫瘍ができても、ほとんどの犬は元気です。
犬の胸からお腹あたりを触っていて、小さなしこりを見つけても犬が元気だとそのまま様子を見てしまうことも多いようです。
犬の乳腺腫瘍の良性、悪性の割合はほぼ半々と言われています。
良性であっても時間の経過とともに悪性に転化する可能性があります。
しこりが小さいうちなら完全切除できる可能性が高まります。
避妊手術をしていない雌犬を飼育している方は、ときどき注意深く犬の胸部から腹部を触ってみてください。
その際に、小さなしこりを発見したらかかりつけの獣医師に相談してみましょう。
犬の大きさ

犬ほど、その種類によって大きさが全く異なる動物も珍しいのではないでしょうか?
小型犬と大型犬では何倍も体重が違いますよね。
チワワも犬、ゴールデンレトリーバーも犬です。
同種でここまで大きさに違いがあるのですから、かかりやすい病気に違いがあっても不思議ではないかもしれません。
小型のシニア犬によくみられる病気

僧帽弁閉鎖不全症
犬の心臓にある僧帽弁という弁が動きに異常をきたし、しっかりと閉じなくなることでおこる病気です。
僧帽弁が閉じなくなることで血液の逆流が生じ、心臓が肥大して気管支にも悪影響を与えます。
そのため、この病気になると犬は咳をするようになります。
ミニチュアダックスフンド、マルチーズ、シーズー、トイプードル、チワワ、キャバリアなどの小型犬に多くみられます。
キャバリアにいたっては、高齢犬だけでなく3歳くらいの若い犬でも発症することがあるので注意が必要です。
僧帽弁閉鎖不全症はほっておくと肺水腫になって命に関わってくる病気です。
治療は生涯にわたって必要になることがほとんどですが、初期段階から治療を開始すると延命効果も高まります。
進行すると、だれでもわかるくらいしょっちゅう咳をするようになりますが、できればそうなる前の軽い段階で受診することをおすすめします。
初期段階では普段は症状がみられませんが、朝方咳をするとか、興奮した時にだけ咳をするといった症状がみられます。
また、犬の咳は人のようにわかりやすい咳ばかりではありません。
実際には吐くものはないのだけれど、吐くようなそぶりを何度もするといったようなこともあります。
このような様子が何日もみられるようでしたら、動物病院につれていきましょう。
関節疾患
関節疾患のなかでも、小型犬に多いのは膝蓋骨脱臼です。
膝蓋骨(いわゆる膝のお皿のこと)が外れてしまう状態になるのですが、犬の場合ほとんどが内側に外れます。
膝蓋骨脱臼は先天性のものがほとんどですが、脱臼のしやすさによっていくつかのグレード(段階)にわけられています。
グレード2以上の場合は子犬のうちに手術をすることが推奨されています。
膝蓋骨脱臼の犬ははしゃぎまわったりしたあとに、片足をあげてスキップするみたいに歩くことがあります。
しばらくすると自然に膝がもとの位置にもどって普通に歩けるようになることが多いのですが、年齢を重ねるうちに膝に負担がかかり片足で歩くことが増えるようになります。
完治させることはできないので、普段からなるべく膝に負担がかからないようにしてあげることが大切です。
小型犬は室内で飼育されていることがほとんどなので、そのことも膝への悪影響となっていることが少なくありません。
フローリングの床などのすべりやすい環境は関節を痛める原因となります。
床は絨毯かマットを敷くなどして、足がしっかり踏ん張れるように工夫することです。
また、ソファーから飛び降りたり、階段の上り下りなどもシニア犬の膝を痛めることになります。
そういったことができないように住空間の工夫が必要です。
大型のシニア犬がかかりやすい病気

関節疾患
小型犬には膝の関節疾患が多いのですが、大型犬は膝に限らず、前肢の手根関節や股関節などの関節も年齢とともに炎症をおこしやすくなります。
大型犬は体が大きい分、関節への負担も多くなってくるのです。
加齢とともに関節軟骨も柔軟性を失ってくるため、関節に直に負荷がかかる状態となります。
そのような状態でも関節は使い続けられるので、だんだんと変形していきます。
痛みが出てくると犬は歩きたがらなくなり、そうすることで筋力も衰えてきます。
関節も筋肉にサポートされているので、筋肉が減ってくるとますます関節への負担が大きくなります。
加齢とともに関節に変形を生じることを完全に防ぐことはできません。しかし、日々の養生でその進行を遅くすることは可能です。
養生の第一歩は体重管理です。やはり、肥満は関節に一番負担をかけてしまいます。飼い主さんは、犬を太らせないようにフードを調整してあげてください。
次に環境です。
最近は大型犬も室内で飼われる方が多くなりました。
小型犬のところでも書きましたが、フローリングの床などは犬が滑りやすく関節に負荷がかかりやすいです。
犬は本来は土の上を歩いています。
アスファルトを歩くことも足の関節にはよくないとは思いますが、現代社会ではある程度は仕方ありませんね。
せめて普段の生活の場では、足がしっかりと踏ん張れるよう工夫してあげてほしいと思います。
また、変形性脊椎症といって、背骨を形成する椎骨のゆがみによって神経が圧迫され、腰が痛くて歩けなくなってしまう病気もあります。
老犬になれば程度の差はあれ、どの犬にも起こることではあるのですが、大型犬にはその影響が大きくでやすいのです。
腰が痛いため、犬は後ろ足の歩幅が小さくなり、立っているときもブルブルと足を震わせるようになります。
大型犬がそうなった場合、立ち上がるのが困難になることもあるのです。
痛みを軽減するために、鎮痛剤の投与が必要となることも少なくありません。
薬はやむを得ませんが、犬が立ち上がりやすいように生活場所をすべらないようにすることが大切です。
すべてのシニア犬に共通する病気

オス、メス、小型、大型にかかわらず、シニア期にはいったすべての犬に共通する病気について説明します。
消化器疾患
犬も高齢になると、消化器機能が衰えてきます。
そして、消化機能が低下すると、ストレスに弱くなってくるように思います。
ストレスはお腹に影響を与えるので、ストレスを与えないように、若いときよりも気をくばってあげる必要があるかもしれません。
加齢とともに腸内細菌のバランスも崩れ、そのため下痢や便秘をしやすくなります。
犬は下痢になることが多いようです。
ただ、高齢犬が下痢をした場合、すぐに動物病院につれて行くのも考えものです。
犬が普段とすこし様子が違うと、その日のうちに動物病院を受診される飼い主さんがいますが、先述したとおりシニア犬はストレスに敏感になっています。
動物病院までの移動や診察で症状が悪化することもありうるので、2~3日自宅で様子をみることも大切なことです。
犬が下痢をしても、元気、食欲に問題なければ少し様子を観察してみましょう。
ただし、犬が明らかに元気がなかったり、普段だったら喜んでたべるおやつにも見向きもしないといった場合には、様子をみずに動物病院につれていってください。
また、元気や食欲はあっても、便に血がまざっているような場合も早めに受診されたほうがいいです。
皮膚疾患
シニア犬の皮膚は、若い犬よりも薄くなって乾燥しています。
皮膚のバリアが薄くなったぶん、細菌による感染症なども引き起こしやすくなっています。
特に、寝ている時間が多くなるシニア犬では、1ヶ所の皮膚に負担がかかり、いわゆる「床ずれ」をおこしてしまうことも珍しくありません。
細菌感染などを伴った皮膚病では、たいていの犬は体を痒がるようになり、飼い主さんもその様子をみて動物病院につれてくることが多いです。
しかし、かゆみを伴わずただ脱毛が進行していくだけの場合は、長期にわたり様子をみてしまわれる方が多いように感じます。
まぁ年だから毛が薄くなってきてもしかたないか、といった感じで特に動物病院に行くほどでもないと思ってしまうようです。
そういうシニア犬の血液検査をしてみると、脱毛の原因はホルモン異常による甲状腺機能低下症やクッシング症候群という病気だったということもあります。
これらの疾患は皮膚だけではなく、全身に影響を及ぼす病気です。
早期発見が大切となってきますので、犬が最近やたらと毛が抜けてきたなと思ったら、動物病院で検査を受けるようにしてください。
癌(悪性腫瘍)
癌といっても腫瘍ができる場所も症状もさまざまです。
若い犬でも癌になることはありますが、やはりシニア犬に多い病気の一つです。
皮膚にできる癌や、乳腺腫瘍のように発見しやすいものもあれば、肝臓癌のように検査をしない限りわからない癌もあります。
犬が慢性的に嘔吐している、食べてはいるけど痩せてきているなどといった症状がみられたら獣医師に相談してみてください。
白内障
白内障とは水晶体のタンパク質が変性して白く濁った状態のことをいいます。
人ではほとんどが加齢によるものですが、犬の場合は遺伝も関わっているようです。
トイプードル、ヨーキー、シーズー、柴犬などは白内障になりやすい犬種として知られています。
また、犬は糖尿病になるとほとんどの場合、白内障を併発します。
犬の目が白く濁ってきたなと感じたら、まずは全身性の疾患にかかっていないか動物病院で調べてもらいましょう。
老齢性白内障の場合は完全には予防できません。
ただ、進行を遅らせる目薬やサプリメントがあるのでそれらを使用することもあります。
手術に関しては、獣医眼科専門医で検査を受けることになります。
認知症(痴呆症)
高齢犬でしばしば問題となるのが、夜鳴きです。
犬が一晩中鳴いて、近所からもクレームがくるといった相談を受けることがあります。
犬が痴呆になった場合にみられる行動を以下に示しておきます。
- 同じところをグルグルと回っている。
- 壁があるのに前に進もうとする。後退ができない。
- さっき食べたばかりなのにまた欲しがる。食欲が若い時よりある。
- 飼い主からの呼びかけに反応しなくなった。
- 今まで鳴いたことのないような声で鳴き続ける。
- 狭いところに入りたがる。
認知症になるのはほとんどが日本犬です。
柴犬か、柴犬系統のMIX犬の相談が一番多いと思います。
痴呆症を完全に治療したり予防するのは難しいのですが、サプリメントが効果的なことがあります。
EPA、DHAといった不飽和脂肪酸のはいったサプリメントを、日本犬がシニア期に入ったら与えておくと痴呆症の症状を緩和できることがあります。
EPAやDHAは魚に多く含まれているので、日本犬には魚肉中心のフードのほうが合っているのかもしれません。
認知症になると、犬は思わぬ行動にでることがあります。
今まで室内を自由にさせていた場合でも、犬がどこかにぶつかって怪我をしないように、サークルで囲むなどの工夫をしたほうがいいでしょう。
最後に

若いうちは予防目的でしか動物病院を利用されなかった方も、犬が年をとると病気治療のために連れて行く機会がふえると思います。
特に犬が避妊、去勢をしてあるかというのは、獣医師が診断を下すうえで重要となります。
シニア犬を飼っている方が初めての病院を利用するときには、しっかりと伝えるようにしてください。
ご自分の犬がかかりやすい病気を知っておくことで、食事を見直したり、飼育環境を整えるなどの早めの対策ができると思います。
参考にしてみてください。
関連記事
・20代独身男性と犬のスローライフ…丁寧な暮らしが『理想的すぎる』と26万再生「心がリセットされる」「幸せな時間」「ほっこりした」と絶賛
・犬が飼い主に体をこすりつけるときの心理とは?状況から考えられる病気も
・どうしても家族に甘えたい犬が、脚を…気づいてもらうために見せた『まさかの催促方法』が66万再生「トントン上手w」「頭脳派で可愛い」と爆笑
・犬は一緒に寝る人を選ぶの?その心理について解説
・妻が犬とチューしようとしただけなのに…まさかの『回避方法』が想定外すぎると67万再生「考え抜いた結果w」「逆に待ってる説」と爆笑の声