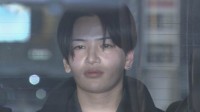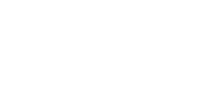【獣医が解説】犬を『長生き』させるために気を付けたい事|家庭で出来る対策や注意点
犬種によって平均寿命は異なりますが、最近では獣医療の発達もあり、少しずつ平均寿命が長くなりつつあります。お家でわんちゃんと一緒に暮らしている飼い主さんであれば、少しでも長く一緒に生活できたらと思う願いは誰でもあるものではないでしょうか。どんなことに気を付ければ少しでも長生きしてもらうことができるのでしょうか。
長生きとは?シニアになって何を望む?

一言で「長生き」と言っても、望むスタイルは家庭によって様々でしょう。
どんな風にシニア期を過ごしてほしいか、そしてどんな風に看取りたいかということも含めて考えることが大切です。
考えただけで悲しい気持ちになる飼い主さんがほとんどだと思いますが、後悔の無いよう、実際にシニア気になる前からきちんと考えることが大切です。
どんな生活をしてほしい?
おうちのわんちゃんがどのようにシニア期の生活を過ごしてほしいか、わんちゃんの性格を考慮しながら考えてあげましょう。
もちろんこんな風でなければならないという正解はありません。
甘えん坊なわんちゃんであれば、少しでも飼い主さんと一緒に過ごせる時間を多く持てるような生活スタイルにしてあげるような見直し、お散歩が好きなわんちゃんであれば、どのように負担なく好きなお散歩をしてあげられるかということなどを考えられると良いと思います。
もしかしたら、普段わんちゃんが過ごす場所の見直しなども必要になる可能性もあります。
飼い主さんがおうちのわんちゃんにしてあげたいことも含めて、考えてみることをおすすめします。
どこまでのことをしてあげたいか
中高齢になるにつれて、体の器官は加齢に伴い機能の低下が起こります。
何らかの持病が見つかったり、その子の健康面で注意が必要なことがわかってくることが多いです。
そんな時にどこまでのことを飼い主さんとしてできるか、してあげたいかということをご家族で話し合っておくことはとても大切です。
治療という意味では、完璧を求めるのであれば高度医療を行い、病気を治すことや治療すべきことが最善の選択肢かもしれません。
ただし、それは本当におうちのわんちゃんやご家族にとって一番の幸せと結びつくとは限りません。
おうちのわんちゃんの性格や、ご家族との関係性などによって、その子にとっての最善と思える策は様々です。
ご家族で望むいずれ迎える「看取り」をどのようなものにしたいか、経済的な面やご家族の背負える負担の面などでどこまでが可能なのか、お話する機会を持つことで、限りあるわんちゃんとの時間がより有意義なものになるでしょう。
病気の種類にもよりますが、緊急性の病気や進行が速い病気の場合、いざ病気が発覚してから治療を選択するまでにスピードが求められることがあります。
予め、どの程度の治療をおこなうのか、費用はどのくらいまでなら出せるのかということをご家族で話し合っておけると診療がスムーズに進む可能性が高いです。
いずれ迎える最期のことを考えただけで悲しい気持ちになる飼い主さんも多いかもしれませんが、わんちゃんの寿命は限られていて、飼い主さんが看取ることになるケースが一般的であり、「看取り」は飼い主さんの責任でもあると言えるでしょう。
わんちゃんの持病がわかったり、健康状態によって、飼い主さんの意識も変わってくる場合もあります。
定期的にお話をする機会を設けられると良いと思います。
家族間での「長生き」の認識
わんちゃんを迎えるとき、ご家族の中の誰かが言い出しっぺになったり、名義上は誰か一人が飼育者という登録になっているかもしれません。
しかし、シニア期を迎えてお家でケアをしたり、持病を管理する必要性が現れると、ご家族で行なう必要が生じます。
また、治療などの費用が生じる場合に、家庭の経済状況との関連もあるため、どなたか一人での決定で行なえる問題ではないケースが一般的です。
大きな病気を少しでも早く防ぐよう、こまめな予防や健康チェックをより重点的に行っていく方針や、病気などがわかっても積極的な治療は行わないという選択肢もあります。
本来、野生の動物たちはもちろん病院などを受診する頻度は低く、自由に生活している代わりに寿命も短い傾向があります。
かかりつけの先生の考える理想的な「長生き」とは、そしてご家族の考える理想的な「長生き」とはどんなものなのかということを話し合ってみることも大切です。
専門家の意見として、現実的に実現可能な「長生き」の形なのか、そのために日常的に行うべき習慣や気を付けることがわかってくるはずです。
また、おうちのわんちゃんの性格を一番わかっているのは飼い主さんと言えるでしょう。
どんなことが強いストレスとなり得るのかや、ご家庭でできる処置や健康管理はどこまで可能なのかをかかりつけの先生にお話したうえで、シニア期に向けて、対策を一緒に考えられると安心です。
家庭でできる健康面での長生きするためにできること

加齢による体力や体の機能の変化は避けられませんが、少しでも元気にシニア期を過ごしてもらいたいという願いはどんな飼い主さんでも持っているでしょう。
そのために、家庭での対策は欠かせません。
どのようなことを気を付けたらいいのでしょうか。
全身状態の把握
どんな病気やトラブルでも「早期発見、早期治療」はわんちゃんの負担軽減のためにも大切です。
加齢によって体の機能の変化は必ず起こります。
気を付けるべき変化は以下の通りです。
- 筋力の低下
- 消化機能の低下
- 体内の器官の加齢による機能低下
- 認知能力の低下
これらは行動の変化や食事量、排泄などで気付くことが多いです。
おうちのわんちゃんの健康な状態を把握しておくと、小さな変化にも気付きやすいです。
抱っこをしたり、一緒にお散歩をしたりするスキンシップの中にもヒントはたくさん隠されています。
ご家族がそろったときにはわんちゃんの最近の様子を話し合ったり、連絡ノートに気づいたことを記録したりして、普段あまり一緒にいられない人も情報を共有できると安心です。
健康状態に合わせた生活の見直し
加齢とともに、お付き合いしなければならない持病が見つかったり、機能の低下などで今までと生活環境を変える必要性がある可能性もあるでしょう。
例えば、階段を自由に上り下りできるようにしていた場合、四肢の筋力低下や関節の違和感などで難しくなったり、制限をする必要があるかもしれません。
また、認知症などで昼夜逆転が起こったり、排泄が上手くできなくなる場合は、今まで別々に寝ていた飼い主さんも、一緒の部屋に寝るなどの環境の改善は必要なケースが多いです。
引っ越しをしたり、リフォームをするという大掛かりな改善までは行わなくとも、床が滑らないようにマットを敷いたり、段差をなくすための台を置いたりという小さな模様替えは、行うとわんちゃんもストレスフリーに過ごせる可能性が高いです。
お留守番をさせづらくなるケースも考えられます。
その場合、ご家族のお出かけ時間の調整や、どうしても不在にしなくてはならない時の預け先の確保などもできると安心です。
シニア期でも安心できるかかりつけの動物病院を見付けておく
どんなわんちゃんでも、いつどんなトラブルに遭遇するかわからないですが、シニア期になると、より一日一日の変化に注意が必要になることが多いです。
ちょっとした変化に気づいた時に、気軽に相談できる専門家が身近にいるととても心強いです。
できれば、シニア期になって見つけるのではなく、長く診ていただいている先生であれば、わんちゃんの性格や健康な時の状態も把握でき、比較して相談に乗ってもらえる可能性が高いです。
特にハイシニアになると、看取りのことも考える必要があるため、飼い主さんの考え方を理解してくれる動物病院や、似たような方針を持っている動物病院であることなども考慮した方が後悔が残らないケースもあります。
また、何を動物病院に求めるかによっても、良い動物病院と感じられる病院に正解はなく、飼い主さんそれぞれに適した動物病院がそれぞれ存在します。
健康な頃から信頼関係を築ける動物病院を探しておくことをおすすめします。シニア期を実際に迎えた時に行うべきこと

おうちのわんちゃんが実際にシニア期を迎えた時に、飼い主さんはどんなことをしてあげるべきでしょうか。
わんちゃんがより負担が少なく生活するために、健康状態に合わせた生活をしてあげることはとても大切です。
フードの見直し
加齢とともに、消化機能が低下したり、太りやすくなるなどの変化が見られることが多いです。
そのため、消化機能に見合った質かどうか、摂取している熱量は適切かということを見直す必要があります。
シニア用のドッグフードは消化しやすいように食物繊維が多く含まれていたり、カロリーオーバーになりにくいようなものだったり、食餌量が少なくなった子が少量の摂取でしっかり熱量を得られるように作られていたり、シニアのわんちゃんたちの体に適したご飯であることが多いです。
また、移動のしづらさや嚥下のしづらさから水をあまり飲まなくなった場合には、水分を多く含むウェットフードへの切り替えを検討しても良いかもしれません。
お散歩時の様子をよく見てお散歩内容の見直しをする
加齢とともに、四肢の筋力は低下し、関節も変形などによって痛みや違和感が生じるようになることから、お散歩を嫌がるようになるケースも多いです。
お散歩のコースによっては、坂道や階段が多いと関節への負担がかかるため、コースの変更をする必要があるでしょう。
心疾患などの持病によっては、興奮を控えるためにお散歩の制限をされることもあります。
筋力の維持という意味でお散歩は大切ですが、健康を害してしまうのであれば制限してあげてください。
お外が好きな子であれば、四肢への負担軽減のためにバギーでのお散歩も気分転換になるかもしれません。
定期的な健康診断
病院が苦手なわんちゃんも多いので、定期的に病院を受診することがハードルが高く感じる場合もあるでしょう。
しかし、わんちゃんは人間で換算すると、小型犬であれば1年で約4歳分、大型犬であれば約6歳分のスピードで成長します。
そのため、若いころは1年に一度の健康診断でも充分に変化に気づけますが、高齢になると1年の間にもさらに変化が見られるようになります。
可能であれば半年に一回、持病がある場合はそれよりもこまめに定期的に検査を行うことがおすすめです。
わんちゃんの向き合っているトラブルによっても、適切な検査の頻度は異なります。
かかりつけの先生とよく相談をして、どの頻度での検査を行って観察をしていくかを決められると良いでしょう。
血液検査やレントゲン検査だけでなく、体を触ってもらったり、歩行の様子を見るだけでも全身の状態を知ることができます。
爪切りなどのタイミングに一緒に全身状態のチェックもしてもらえると安心です。
まとめ

大切な家族の一員であるわんちゃんですが、私たち人間と同じように年をとり、最期を迎えます。
わんちゃんにとって幸せなシニア期を迎えてもらうために、若い頃からしっかりとシニア期のことを考えておくことは大切です。
わんちゃんの性格や飼い主さんたちとの関係性、環境などによって、幸せとされる長生きの形は様々で正解はありません。
飼い主さんそれぞれのスタイルでの充実したシニア期を過ごせると理想的です。
また、シニア期のことを考えるうえで悩んだり行き詰ってしまうこともあると思います。
そんなときは獣医さんやトリマーさんなど周りの専門家の方に相談してみてください。
ご家族だけでなく、それぞれの分野の専門家の方の力も借りながら、一緒に楽しい生活をおうちのわんちゃんと作り上げられると良いですね。
関連記事
・赤ちゃんが手押し車にハマったら、一緒にいた犬が…まさかの『健気すぎる光景』が53万再生「お姉ちゃんしてて泣ける」「めっちゃ優しい」と絶賛
・犬と一緒に寝るって本当にいけないこと?危険性と注意すること
・子犬の前で『飼い主が遠吠えした』結果…衝撃的すぎる『鳴き声』が484万再生「そっちかーいw」「下手くそすぎて草」「ドラムロール爆笑」
・犬が飼い主にお尻をぶつけてくる理由とは?5つの心理を解説
・お風呂が嫌いな大型犬→シャワー中に絶望するも…終わった後の『テンションMAXな光景』が21万再生「ギャップ萌え」「喜びの舞w」と爆笑