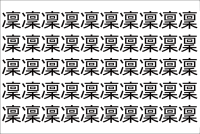伊勢神宮から徒歩1分。土産物店や飲食店が立ち並ぶ「伊勢おはらい町通り」の中でも、ひときわ人気の飲食店「ゑびや大食堂」。
【写真を見る】再建か、廃業か。“昭和のまま”老舗食堂の売り上げを7.7倍に押し上げた、データ活用と需要予測【DIG Business】
100年超の歴史を持つ老舗だが、各テーブルには注文用のタブレットがあり、会計は無人レジ。キッチンには食材の在庫が減ると自動で発注をかける重量センサーなど、いたるところに最新テクノロジーの仕掛けがある。
こうしたDX(デジタル・トランスフォーメーション)によって、2012年に1.1億円だった売り上げは、2023年に約8.5億円と7.7倍に伸ばしている。
企業の思いや開発深掘り深掘りする『DIG Buisiness』。今回は、驚異的な成長の立役者、元ソフトバンクの小田島春樹社長(38)に話を聞いた。
「昭和のまま…」老舗食堂と大手IT会社員との出会い
「昭和のまま止まっている」。当時、ソフトバンクの社員として新規事業などを担当していた小田島さんは、最初に「ゑびや大食堂」ののれんをくぐったとき、そう感じた。妻とともに安産祈願のために伊勢神宮を訪れ、そのついでに立ち寄った。
ただの客というわけではない。実はこの店、妻の両親が営む店だったのだ。以前から、伊勢神宮のそばでうどん店をやっているとは聞いていた。昔ながらの食堂を思い浮かべていたが、想像を超えていた。
食券は手でちぎって渡し、会計はそろばんで計算していた。妻は一人娘。継いでほしいと直接言われたことはなかったと言うが「ビジネスとしてはかなり厳しい。自分がやることはない」そう感じていた。
小田島さんは自らを「根っからの商売人」と話す。幼い頃から祖母が利益や株の仕組みなどの話をよく教えてくれていた。子どもながらに興味を持ち、いつか自分で事業を行いたいと思っていた。大学を出てソフトバンクに入社した後も、その思いは持ち続けていた。そんな中で、妻の両親から「飲食店事業を縮小し、テナント事業を始める」という話が出た。
「自分で事業をやりながらテナント収入が入るならいいな」。そう考え、小田島さんは2012年にソフトバンクを辞め、ゑびやに入社した。しかし、テナント事業は早々に頓挫する。飲食店として再建するか、廃業か。小田島さんはいきなり選択を迫られることになる。
「諦める前に、もう一度きちんと見つめ直そう」。険しいと思われる再建の道を、自ら選んだ。
「昭和のやり方」からの脱却 データ活用で見つめ直した生産性
事業を引き継ぐと決め、改めて食堂を見ると、厳しさを再認識せざるを得ない状況だった。繁盛しているとはいえないこの店に対し、隣は人気店。隣の店に並ぶ行列が、食堂の入り口を塞いでいた。
「昔ながらのやり方では生き残れない」。まず着手したのは、売り上げの管理だ。この店では毎日台帳に手書きで記録を取っていたが、1週間後にはエクセルで記録を残す方式に切り替え、その後POSデータ(販売実績)を管理できるシステムを導入した。
次に取り組んだのはメニューの改革だ。当初この店は、伊勢うどんのほかはカツ丼やカレーライスなどの一般的なメニューを提供していた。小田島さんは、訪れた客から「満足度」や「食べたかったメニュー」などのアンケートを集めた。すると「地元ならではの食材・料理」を食べたかったという回答が多いことに気がついた。
「これまでのやり方は間違っていた」。
小田島さんは確信することになる。伊勢神宮のそばにあるゑびやを訪れるのは約8割が観光客で、多少お金を払ってでもその店でしか食べられないものを選ぶ。いわば「ハレの日」のメニューが求められていたのだと気付いた。
今では食材の約90%は三重県産に。松阪牛のすき焼きや地元の海で取れた食材を使った海鮮丼などが人気のメニューだ。結果的に1人当たり約850円だった客単価は約2850円に増え、自然と売り上げも伸びていった。
台帳と“勘”からデータに基づく需要予測で精度95%に
飲食店にとって、最も痛手なのは食材の廃棄だ。せっかく仕入れた食材が捨てられていくのは、何より懐が痛い。しかし、過度に仕込みを減らして「品切れ」すれば客を失望させてしまう。つまり、どのように“需要を予測する”かが大きなカギを握るのだ。
この店では、料理人らが台帳に残る前年の売り上げと「晴れ」「くもり」などの大まかな天気予報を頼りに半ば“勘”で予想していて、人によって意見が分かれることも多かった。
これまで感覚や経験則に頼ってきた判断を、正確なデータに基づいて計算することができれば、食材の廃棄を減らすことができると小田島さんは考えた。
「データを基に客数を計算するシステムがほしい」。飲食店を受け継いでたった数年の自分が気付いたくらいなのだから、すでに世の中にはそういったシステムがあるだろう。しかし、小田島さんがいくら探しても、そういったシステムは見つからなかった。
「ないなら自分で作ろう」。これが、ゑびやが急成長を遂げるきっかけとなった。
2015年に需要予測のシステムが完成した。曜日や天候、風速などの13項目と前年の売り上げなどから客数を予測。料理ごとの数も予測され、その予測に合わせて必要な量を必要なだけ準備するようになった。直近一年の客数予測の精度は95%に上り、このシステムによって、食材の廃棄は劇的に減った。米の廃棄量は約8割減ったという。
ほかにもDX化を積極的に進めている。店内に置かれたセルフサービスのお茶の下には重量を量るセンサーがあり、一定の重さを下回ると調理場に通知が届き、従業員が補充に向かう仕組みだ。同様のセンサーは調理場のほぼ全ての食材や調味料にも使われていて、量が減ると自動で発注されるようになっている。
小田島さんの改革はすぐに実を結ぶ。売り上げは年々伸び、利益率は10倍になった。2018年には「TOUCH POINT BI(タッチポイントビーアイ)」と名付けた需要予測システムを飲食・小売業に販売する「EBILAB(エビラボ)」という新会社を立ち上げた。こうした事業も相まって、小田島さんが入社した2012年に1.1億円だった売り上げは、グループ全体で約8.5億円(2023年)と7.7倍にまで増えた。
連日、ゑびやには全国各地の飲食店などが視察に訪れていて、システムを導入する飲食店も増えている。例えばサービスエリアやパーキングエリアを運営する西日本高速道路サービス・ホールディングスは、福岡県朝倉市にある山田サービスエリア(下り)に試験導入し、食材の廃棄ロスの削減に取り組んでいる。
また、社員や職員のデジタル教育に使いたいと講演やコンサルティングの依頼も。中には三菱地所やイオン九州などの大企業の名前もある。
このシステムを導入した企業は全国で300を超えている。
「中小企業だからこそ挑戦できる」
「仕組みを作って楽をするというのが、僕が目指すビジネスなんです」。客の年代や料理ごとの注文数、食材の在庫など、さまざまなデータが並ぶパソコン画面を前に、小田島さんはそう語った。
「誰しも買い物や投資をするときに人気のランキングなど、何かのデータを参考にしていると思う。データを使うのは僕にとっては当たり前だった」
小田島さんは、ゑびやへの入社以来、客からのアンケートを大切にしている。気象データや来客予測はもちろん、直接聞き取れる客の声も重要なデータのひとつなのだという。最近でも、客の要望を受け、注文方法をスマートフォンでQRコードを読み取る方式から、各テーブルにタブレットを置く方式に変更した。
小田島社長は「中小企業だからこそ挑戦できる」と話す。大企業の方が意思決定に時間がかかり、変化をしにくい場合もある。中小企業であれば、経営者さえ認めれば、すぐに動くことができる。
伊勢にあるゑびやの周りでは、経営難や人手不足、後継者不在などが原因で入れ替わった店も少なくない。こうした課題が山積している地方の中小企業の方が「変わらなければ生き残れない」という危機感もあり、むしろ積極的に挑戦できる環境にあるのではないかと指摘する。
ゑびやのDX化の取り組みは「第3回 日本サービス大賞」で地方創生大臣賞を受賞するなど高い評価を受け、日本マイクロソフトや全国の自治体との協業も行っている。伊勢の老舗飲食店は、飲食店の困りごとをデータ分析やテクノロジーで解決するベンチャー企業に生まれ変わった。
「データを活用する」「欲しいシステムがないなら自分で作る」。一見するとハードルが高いようにも思えるが、「客からアンケートを取る」など、すぐにでも取り組めそうなこともある。悩みを抱える中小企業の生き残りのヒントとなるかもしれない。