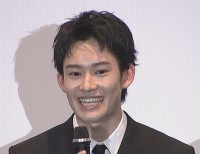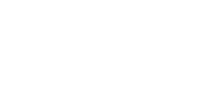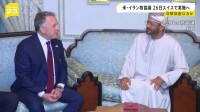2025年の放送界を振り返り、2026年を展望する~フジテレビ問題、戦後80年、選挙報道の改革など~【調査情報デジタル】

2025年は放送開始から100年目であった。その節目の年に、フジテレビ問題で放送界に激震が走った。さらに2024年の選挙報道に対する反省の上に立った選挙報道の改革も進んだ。それらの動きを振り返り、放送と通信の融合がますます進化することなどが予想される2026年を展望する。上智大学・音好宏教授の論考。
スタートから100年目を迎えた日本の「放送」
2025年は、放送にとって節目の年であり、また、激動の年でもあった。
日本で放送がスタートしたのは、1925年3月22日。社団法人東京放送局(JOAK)の開局で始まる。昨年は、それからちょうど100年目であった。
JOAKの初代総裁を務めた後藤新平は、開局式の挨拶で放送事業に関する4つの職能として、「文化の機会均等」、「家庭生活の革新」、「教育の社会化」、「経済機能の敏活」の4つを挙げている。この年、日本で普通選挙法が制定され、全ての成人男子に政治参加が認められた。機を一にして、放送は全ての人にその便益を享受することが示された。
言わば、放送という新たなサービスにより、全ての人々の社会生活をより豊かにする可能性を予見し、それゆえに放送サービスには公共性・公益性が求められると認識していたのである。
新しいものが好きで、「大風呂敷」というあだ名があるようにスケールの大きな話を好んだとされる後藤は、放送という新しい事業に強く惹かれていたし、また、その事業への意気込みも強かったのであろう。当時の新聞は、開局式での後藤の姿を「反り身の演説」と、その緊張ぐあいを報じている。
問われた放送局のガバナンス
さて、この日本最初の放送から100年目の2025年は、後藤が示した放送の公共性・公益性に基づく放送への信頼を揺るがす事態からスタートした。フジテレビ問題である。
複数のテレビ番組にレギュラー出演をしていた人気タレントの中居正広氏が、フジテレビの女性アナウンサーに対して性的暴行を行ったとする疑惑を、2024年末に一部週刊誌が報道。
それを受ける形で開かれた1月17日のフジテレビの社長会見には、記者クラブ加盟の記者のみに参加が許され、しかも、映像取材を禁ずるという日ごろ取材対象者にオープンな取材を求めている報道機関としては考えられない、後ろ向きの姿勢であった。
このフジテレビの対応には、内外から激しい非難が巻き起こり、1月27日にフジテレビは、再度会見を行い、経営トップが会社全体のガバナンスを機能させることができなかったことを踏まえて、フジテレビの代表権を持つ嘉納修治会長、港浩一社長の辞任を発表するとともに、本件の調査にあたっては、日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインに基づく第三者委員会を立ち上げたことを発表した。
この間、フジテレビにCM出稿をしていたスポンサーによるCMの見合わせ、差し替え要請が相次ぐことになる。在京民放キー局において、大規模なCM出稿の取りやめが起こったことはこれまでになかったことであり、民放局の経営基盤そのものを揺るがす事態であった。フジテレビを傘下に置く認定放送会社のフジ・メディア・ホールディングス(FMH)は上場企業であり、そのコーポレート・ガバナンスが内外から非難されることになる。
調査にあたった第三者委員会は、3月31日に報告書を公表。その内容は、当該事案が人権侵害にあたるハラスメント事案であったと結論づけるとともに、調査で明らかになったフジテレビ社内で起こっていた他のハラスメント事案についても言及し、それらに対処できなかったフジテレビのガバナンスの欠如を問題とした。この報告書によって、1月から始まったスポンサーによるフジテレビへのCMの見合わせは続くことになる。
他方で、このフジテレビ問題に関しては、放送局の信頼を損ねるものとして、会期中の国会でもたびたび取り上げられ、与野党からフジテレビ、ひいては、放送事業全体のガバナンスに対する厳しい声が相次いだ。
特に今回のフジテレビ問題は、民放連会長社で起こった事案でもあり、業界団体である民放連の向きあいも問われることとなった。そのようななかで、総務省は「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」を設置。放送事業者のガバナンスのあり方について検討されることとなる。この検討会で焦点となったのは、放送事業者による自律性を最大限尊重しつつ、ガバナンスの確保することにあった。
この問題は、2026年まで後を引くことになる。民放連は、2026年1月に、定款変更を行うとともに、「民間放送ガバナンス指針」を策定。4月から第3者を交えたガバナンス検討審議会など、ガバナンスの強化策を示すことになる。
他方で総務省は、前述のガバナンス確保に関する検討会を発展させる形で、円卓会議を設置して、放送界の自律的なガバナンス確保が適正に進められているかを確認する形となる。
この件については、放送事業者個社のガバナンス強化が図られていくのか、民放連、総務省が示した枠組みが上手く機能していくのか。今後の成り行きが注目されよう。
「戦後80年」とどう向きあったか
2025年は、戦後80年目という節目の年でもあった。取材現場には、戦争体験者から生の証言を聞ける最後の節目という思いもあったようだ。各報道機関は、様々な形で「戦後80年」を扱ったが、各社・各局の体力や姿勢には随分と違いがあり、その扱う量も質も千差万別であった。
個人的な印象だが、全国紙では「朝日」、「毎日」、「読売」の3大紙が、放送局ではNHKとTBSテレビが、群を抜いて扱いが多かったように思う。NHKは、テレビ放送だけでも、地上放送2波、BS放送2波と保有チャンネルが多く、また、受信料を財源としていることもあって、放送枠の確保が民放テレビ局より容易かも知れない。
他方、TBSテレビは、「戦後80年 つなぐつながる」というプロジェクトを掲げ、8月に特番を組むといったいわゆる「8月ジャーナリズム」に留まることなく、2025年の1月から12月まで、年間を通して「Nスタ」「news23」といったニュース番組枠の特集コーナー等で、この企画テーマでの映像レポートとして扱われていた。加えて、それらの映像レポートは、TBS系のニュースサイト「NEWS DIG」でも展開された。
他方でNHKは、ネット上での動画配信サービスが必須業務化されたことで、2025年10月より「NHK ONE」が開始されたが、そのスタートには新聞業界などから「民業圧迫とならないよう」などの注文もあり、NHKのネット展開には、制限がかけられたこともあって、ネット上での新たなコンテンツ提供はできなかったものの、「戦後80年」に係る意識調査や過去の戦争関連番組のアーカイブ配信を行い、高い評価を得ている。
2026年は、戦後81年目にあたる。80年目の節目で、力を入れて報じたメディアが、今年、「戦後」とどう向きあうのか。「8月ジャーナリズム」を含め、その姿勢が問われることになろう。
選挙報道の見直し・改革の動きが本格化
SNSが普及・浸透するなかで、その政治的影響力が顕在化したのが、2024年に行われた選挙であった。石破茂政権が発足直後に打って出た10月の衆院選、斎藤元彦兵庫県知事の失職に伴い行われた11月の兵庫県知事選は、SNS選挙といわれた。
特に、兵庫県知事選挙では、立候補したN党の立花孝志氏が、再び立候補した斎藤氏を応援するいわゆる「二馬力選挙」を展開。立花氏は、YouTubeなどで、斎藤氏の失職に至る内部通報者らを非難する発信を続ける一方で、既存メディアを敵視する発言を繰り返した。これらの言動が、少なからず兵庫県知事選に影響を与えたとされ、斎藤氏が知事に再選されるに至る。
これまで、既存メディアの選挙報道は、公職選挙法に加え、放送に関しては、放送法4条が「政治的公平性」を規定していることもあって、その取り上げ方は、慎重にならざるを得なかった。2017年2月にBPO放送倫理検証委員会から、選挙報道における「質的公平性」(実質的公平性)を求める意見が出されてはいたものの、放送局の選挙報道では、投開票日までは、立候補者の扱いを公平にすることに主眼が置かれ、その報道量が減る傾向にあった。
このようなこともあって、2025年7月の参院選においては、新聞・放送といった既存の報道機関で、選挙報道のあり方が再検討され、公示期間中であっても積極的に報ずる姿勢が示された。
この試みによる混乱はほとんどなく、選挙後の有権者に対する調査でも、おおむね好評であった。今後の選挙報道においても、しばらくは試行錯誤が続くかも知れないが、公示期間中であっても、より積極的な報道がなされる方向に進むことが予想される。
他方、2024年の兵庫県知事に対するパワハラ疑惑に関する内部告発に端を発する一連の兵庫県問題に関しては、TBS「報道特集」が、キャンペーン報道を展開。虚偽文書のSNSでの拡散など一連の問題の連鎖を粘り強く取材・報道し続けた。
これらの報道に対しては、ネット上を中心に様々な批判や誹謗中傷、番組関係者への個人攻撃なども少なくなかった。それらの批判に晒されながらも、報道機関として、事実に基づいた取材・報道を続けたことは特筆できよう。これらの一連の報道は、「ギャラクシー賞」「早稲田ジャーナリズム大賞」など、いくつかのアワードで高い評価を受けることになる。
他方で、2025年11月、N党の立花孝志氏が虚偽発言などで、故・竹内英明元兵庫県議の名誉を傷つけたとして逮捕、起訴される。
「世界陸上2025東京」で問われた放送局とスポーツイベントの関係
2025年も、多くのスポーツイベントが放送を賑わした。
大谷翔平選手のメジャーリーグでの活躍が、連日のスポーツニュースを賑わしたが、ロサンゼルス・ドジャースで、大谷選手のチームメートとなった山本由伸投手も活躍した。特に、ワールドシリーズでのタフネスな活躍は目覚ましく、ドジャースの2年連続優勝に大きく貢献。日本人投手として初となるワールドシリーズMVPも獲得したことが、大きく報じられることになった。
また、スポーツイベントをテレビ中継するだけでなく、放送局が半身乗り出してイベントとの開催・運営に関わったものとして、「世界陸上2025」を挙げることができよう。
9月13日から21日の9日間、東京・国立競技場を舞台に開催された「世界陸上2025」では、TBSテレビが独占的に放送権を持つだけでなく、同大会の開催そのものに関与。大会の盛り上げに一役買った。
そのようなこともあって、結果、日本選手が獲得したメダルは、銅が2個だけという少々寂しいものであったが、大会は大いに盛り上がるとともに、放送への接触率も高かったことが報じられている。
単にスポーツイベントの中継を編成するのみならず、大会の開催そのものに、より踏み込んで関わることで、エスノセントリズム(自民族中心主義)に陥りがちな国際スポーツイベントから、多様・多彩な魅力を引き出し、視聴者・観客を集めたことも、放送局における未来志向の取り組みとして期待したい。
ところで、この「世界陸上2025」において、実況を担ったTBSテレビでは、400メートル障害など、いくつかの競技において女性アナウンサーを実況に起用。これまでスポーツ実況には、NHKを含めて女性アナウンサーが起用されることは、極めて少なかった。
その理由として、これまでしばしば指摘されてきたのが、女性の声質がスポーツ実況に馴染みにくいというものだったが、今回の試みは、おおむね好評で、今後につながる試みとなったと言えよう。
他方で、今後のスポーツイベントと放送との関係に関して大きな問題は、放送権料問題である。いま、スポーツイベントの放送権料の高騰は、放送界を悩ませ続けている。
2026年3月、野球の国・地域別対抗戦、第6回ワールド・ベースボール・クラシック(以下、WBC)が開催される。日本代表「侍ジャパン」は、前回大会の優勝に続いて2連覇に挑む。ただ、今回のWBCの放映権は、Netflixが独占することが決まっており、地上テレビで、試合が完全中継されることはなさそうである。
グローバルな配信サービスが、コンテンツ市場での支配力を強めるなかで、欧州諸国と同様に、日本においても、国民的なスポーツイベントに誰もがアクセスできる環境をどう確保するかという問題が浮上するかも知れない。
衛星放送事業の再検討
2025年は、様々な節目の年であり、2000年12月1日にスタートしたBSデジタル放送も、その開始から25周年を迎えた。
BS民放各局は、周年記念番組などを編成するところも少なくなかったが、他方で、25年9月から再開された総務省の「デジタル時代の放送制度の在り方に関する検討会」の下に置かれた「衛星放送ワーキング」(以下、衛星WG)において、BS4K放送の今後について検討がなされた。
その背景にあるのは4K放送の普及の伸び悩みである。2003年にスタートした地上デジタル放送は、2011年のアナログ停波を目標にデジタル放送への移行が進められた(この年の3月に起こった東日本大震災によって、岩手、宮城、福島の被災3県は、2012年3月をもって地上アナログ放送を終了)。前後して、来たるべき放送のあり方として掲げられた目標の1つが、放送の「超高精細度化」だった。
この目標に沿って環境整備がなされ、2015年よりCS放送、ケーブルテレビで4Kの実用放送がスタート。続いて、2018年からはBSの右旋・左旋円偏波を使って4K放送がスタート。BS右旋には、NHK、民放BS各社が参入した。他方で、BS左旋円偏波ではNHKによるBS8K放送が開始された。
しかし、若者を中心とした「テレビ離れ」や動画配信の伸張などといったメディア環境の変化のなかで、4K放送の普及は伸び悩む。加えて、2020年に予定されていた東京オリンピックの開催が、4K放送の普及に弾みをつけると期待されていたが、コロナ禍の影響もあって、普及の起爆剤とはなり得ないまま終わってしまう。
2025年7月に再開された衛星WGでは、4K放送、並びに4Kコンテンツの現状を踏まえて検討。10月には、BS4K放送を放送サービスの「太い幹」としつつ、映像コンテンツ制作の世界的な標準となりつつある4Kコンテンツの多角的展開を図っていくことなどが、衛星WGの「第2次取りまとめ案」としてまとめられ、パブリックコメントを経て、12月には、この取りまとめ案が了承された。
ただ、この衛星WGの開催期間中に、その論議に意図的にぶつけられる形で、民放BS局の4K放送撤退の動きが報じられた。
民放BS局による4K放送は、広告モデルによるサービスということもあり、4K放送用の受信機の普及が広告主を呼び込む基礎条件となるのに加え、「ピュア4K」と呼ばれる4Kで制作された魅力あるオリジナル・コンテンツが視聴を引きつけるのであるが、この割合がなかなか上がらなかった。勢い、民放BSの4K放送は、民放BSの2K放送をアップコンバートしただけのサイマル編成が中心となっていた。
他方、前後するが、その2KでのBS放送に関しても、経営環境の悪化から、2025年2月には、6月末をもって「BS松竹東急」が停波することを発表していた。それが急転直下、「BS松竹東急」の株をJ:COMが買収。7月より、同チャンネルは居抜きする形で「JCOM BS」としてサービスが継続されることになる。
2026年には、この衛星WGの第2次取りまとめを受けて、BS4K放送を含めた4Kコンテンツの出し口の拡充に向けた方策が検討されることになろう。他方において、トラポン内のチャンネルの再整理、インフラコストの低廉化に向けた取り組みが進められよう。
CTV化の進行と新たな放送市場の模索
通信と放送の融合が語られて久しいが、動画配信サービスの普及・浸透のなかで、2026年、テレビ接触のCTV(コネクテッドTV)化がますます進展することが予測されている。そこでは、テレビ受像機のリモコンに、Netflixなど各動画配信事業者の専用ボタンが設けられたことなどもあり、動画配信サービスの伸張は著しい。
もちろん、既存の放送事業者もこの領域への展開は重視しており、民放各局は独自のオンデマンド・サービスを展開するとともに、民放公式ポータルサイトのTVerへの番組提供をこれまで以上に積極的に展開する方向に進んでいる。特に2025年は、2015年にTVerがサービスを開始してから10年目の節目を迎えた。TVerもそのことを意識して、提供するコンテンツの拡充を図ってきた。
前述したようにNHKは念願だったネット配信業務の本来業務化が認められ、2025年10月から、それまでのNHKのネット配信サービスである「NHK+」を「NHK ONE」にリニューアル。ネット上でのサービスの深化を目指している。その移行に当たっては、若干の混乱も報じられたが、このサービスの安定化と充実は急務であろう。
NHKは、前田晃伸会長時代に行った改革により、組織のスリム化と受信料の値下げが行われ、営業収入が減少したなかで、今後、視聴者に満足してもらえるサービスを提供しつつ、健全な組織運営をどのように行っていくのかに注目が集まっている。
2026年に入って早々に、井上樹彦氏がNHK会長に就任する。井上氏のNHK会長就任によって、18年ぶりにNHK出身者が会長に着任することになる。早々にその手腕が問われることになろう。
他方で、民放に目を向けてみると、民放事業者の経営環境が厳しさを増していることも確かである。
特にローカル民放局の経営環境は厳しく、近年、前述の総務省「デジタル時代の放送制度の在り方に関する検討会」などで、マスメディア集中排除原則の緩和策などが検討され、具体的な施策が進められているが、2025年には、条件不利地域において小規模中継局をNHKと民放で共同利用する計画の検討が進められた。NHKの出資等に関して経営委員会から異論が出るなどして一度は頓挫しかけたものの、2025年の年末になって、出資形態を変えることで最終的には合意に達した。
民放公式ポータルであるTVerを介して、ローカル民放局の制作するコンテンツが全国に支持されるという現象も、徐々にではあるが見られるようになってきている。TVerのみならず、動画配信サービスのなかで、ローカル局のうま味をどう作っていくのかが問われることになろう。
そのようななかで、2026年1月、総務省が音頭を取る形で「放送・配信システム産業競争力・強化促進協議会」が設立されることが決まっている。国内で制作された映像コンテンツを海外市場での展開をも含めて、その流通の活性化・促進を図っていこうというものである。
ただ、日本の映像コンテンツに関しては、文化的な違いなどもあり、国際市場において、なかなか受け入れられないとの声も少なくない。しかし、日本製の文化的な資産が国際的な市場力を持っていないのかといえば、そこはやりようがまだまだあるのだろう。
2023年、ディズニーが制作したシリーズ「SHOGUN 将軍」は、カナダで制作された本格的な日本時代劇で、24年~25年に発表されたアワードで賞を総なめ。特にエミー賞では、作品賞など18部門での受賞という歴史的快挙となった。受賞後、日本の時代劇作りの技術にこだわった妥協を許さない制作姿勢が、しばしば話題となった。
2026年に入って、再びカナダで、「SHOGUN 将軍2」の制作がスタートするという。
これまで、日本のテレビ番組作りでは、実費回収主義に基づいた制作費の調達・回収、息の長い展開とは無縁の著作権処理、少し変化をしたとはいえ終身雇用・年功賃金が前提の人材育成など、放送産業独特の仕組みが続いてきており、それらがいまだに幅を利かせているのは確かである。
しかし、今後テレビを取り巻く環境が激変するなかで、自らが制作に携わった映像コンテンツを、文化資産として積極的に展開していくことに、その将来性、可能性があることは確実である。
2026年が、テレビの将来を見据えた放送システムの抜本的改革の年になっていくことを期待したい。
<執筆者略歴>
音 好宏(おと・よしひろ)
上智大学新聞学科・教授
1961年生まれ。民放連研究所所員、コロンビア大学客員研究員などを経て、
2007年より現職。衆議院総務調査室客員研究員、NPO法人放送批評懇談会理事長などを務める。専門は、メディア論、情報社会論。著書に、「放送メディアの現代的展開」、「総合的戦略論ハンドブック」などがある。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。