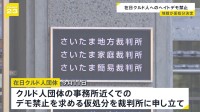GMOインターネットグループが1区間おきに区間賞4個「みんなで助け合う駅伝」で一度もトップを譲らず快勝【東日本実業団駅伝レビュー】

今年のニューイヤー駅伝8位のGMOインターネットグループが、東日本大会初優勝を飾った。第65回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県庁をスタートし、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場にフィニッシュする7区間76.9kmで行われた。
GMOは1区の吉田祐也(27)が3km手前からリードを奪い始め、2区への中継では2位に40秒差をつけた。2区で差を縮められたものの、3区の今江勇人(26)も区間2位を31秒も引き離す区間賞。5区の嶋津雄大(24)、7区の小野知大(25)も区間賞の走りで2位のヤクルトに1分53秒差をつけ快勝。ニューイヤー駅伝でも台風の目となりそうなチームが誕生した。
2位にヤクルト、3位にサンベルクスが続いた。5連覇がかかっていた富士通は4位、SUBARUが5位、優勝候補の1つのHondaは7位。この3チームは、中心選手が加わるニューイヤー駅伝での巻き返しが期待できる。
東日本では価値の高い1区独走
1区・吉田の独走は効果が絶大だった。また過去の1区と比べても、価値が極めて高い走りだった。3km行かないうちに前に出たが、「予定通り」だったと吉田はいう。「後半区間に向けてリードを奪うことと、今日は全員で戦うという意思をみんなに見せる意図があって、こういうレースをしました」2位との差は特に想定していなかったが、10kmを28分を切って通過したいと考えていた。「そのまま行けば区間記録は出る」というイメージ通りに走ることができた。「結果的に2位に40秒差をつけられ、非常に良いレースができたと思います」
好調の要因として1月から、母校の青学大で練習をしていることを挙げる。「(青学大の)原晋監督に一からメニューを見ていただいて、マラソン、10000m、5000mで自己ベストを出せました。学生の頃の延長でやることが良いと思って判断しました。結果も付いてきたので良かったのだと思います」学生と同じメニューを行うが、それに自分でプラスして練習を行っている。距離重視や、スピード重視ということではなく「普通にバランスを考えてやっています」という。
ニューイヤー駅伝1区では数年に1回、独走したり序盤からリードを奪ったりする選手が現れる。だが東日本大会では現行コースとなった08年大会以降(コロナ禍のため周回コースで行われた20年、21年は13.4km。それ以外は11.6km)、1区は混戦が当たり前になっていた。11年大会で前区間記録保持者の佐藤悠基(37、SGホールディングス。当時日清食品グループ)が2位に36秒差をつけたことがあったが、それ以外で10秒以上の差が付いたのは21年大会の13秒差だけ。それ以外の14大会の1、2位は4秒以内の差だった。40秒差は距離にすると240m前後で、簡単には追いつけない差である。Hondaには1分06秒差、富士通には1分18秒差をつけたことで、GMOが優位にレースを進められた。
3区、5区でも区間2位を大きく引き離す区間賞
GMOは2区以降も隙を見せなかった。前述のように1区間おきに区間賞を獲得したのだ。インターナショナル区間の2区で、2位のJR東日本に22秒差まで迫られたが、3区の今江が区間2位を31秒も上回り、2位に上がったロジスティードに1分11秒差とした。400m前後の開きである。「順当に行けばトップでタスキをもらうので、その流れをしっかりつかむことが自分の役割でした。後続のランナーに気持ち的に余裕を持たせることが、大事なポイントでしたね。合格点の走りができました」(今江)
4区の村山紘太(31)は区間8位で、2位を走るロジスティードに39秒差まで戻された。だが5区の嶋津雄大(24)が7.8kmの短い区間ながら、区間2位を23秒も上回る区間賞の走り。2位に上がったヤクルトに1分32秒差とした。6区でも差はほとんど変わらず、7区の小野知大(25)もダメ押しの区間賞。序盤からリードし続ける駅伝は珍しくないが、1区間おきに区間賞をとって差を広げていく駅伝は、そんなに多く見られない。東日本大会のGMOは完成度の高い、強さを感じさせる駅伝だった。
伊藤公一監督(48)は1、3、5区の区間賞は想定していたという。「プラスで7区の小野も来れば」という期待もあった。「2区のジャコブ(・クロップ、23。ケニア)は、5000mは世界陸上で活躍(23年ブダペスト大会銅メダル)できても10000mは走れなかったり、トラックは良くてもロードが苦手だったりします。2区でマイナスが生じてもそれを補うために、吉田と今江を前後に配置しました。劣勢の区間が生じたら、別の区間で補うのが駅伝です。目標だった“みんなで助け合う駅伝”ができたと思います」
GMOは過去のニューイヤー駅伝や箱根駅伝で区間賞を取った選手も多く、個人での実績がある選手が多いチームだった。そのメンバーが1つになることで、駅伝参戦6年目で初めて優勝を手にすることができた。
伊藤公一新監督の経歴と特徴は?
今回のメンバーは村山と小野が旭化成から、鈴木塁人(27)がSGホールディングスから移籍加入した。吉田と鈴木は青学大出身。今江は千葉大大学院を出た経歴を持ち、嶋津は学生駅伝の新興勢力である創価大出身。クロップは前述のようにケニア代表にも選ばれる世界トップ選手である。
チームの特徴を最年長の村山は、次のように見ている。「選手それぞれが駅伝の優勝を経験していることは強みだと思いますし、色々な経験をみんなで話し合ってハイブリッド化されているというか、良い感じで混じり合っています。練習はガンガン若手が引っ張ってくれて、とても勢いのあるチームです。(元10000m日本記録保持者の)自分が苦しい持期もありますが、若い選手の力をもらって練習することで、次はマラソンで結果も出せると思います。(どの選手にも)そういう可能性がある楽しみなチームです」
16年に設立されたGMOは初代監督が五輪代表経験のある花田勝彦現早大監督で、2代目が全日本実業団陸上10000m優勝や、ニューイヤー駅伝区間賞などの実績を持つ亀鷹律良氏だった。伊藤監督は愛工大名電高から亀鷹氏が監督だったアラコ(合併後はトヨタ紡織)に選手として入社し、すぐにスタッフに転身。多くのチームで経験を積んできた。女子チームのデンソーではクイーンズ駅伝で、GMOの選手たちと同様に優勝を経験している。22年に亀鷹氏の監督就任とともにGMOに加わった。
「まだ就任して半年で、新しいことはあえてしないようにしてきました。亀鷹前監督がいらして、創部当時から原晋監督も関わっていただいて、昨年まで大迫傑(Nike)選手にもアドバイスをもらっていた。皆さんの良いところを吸収しながら、今までやってきたことをブラッシュアップする形でやっています。積み上げてきたものが出せて、良かったと思います」ブラッシュアップの1つに、練習の設定タイムを少し上げることがあったし、原監督らチームに関わってくれる人たちの力を上手く引き出したり、融合させたりすることがあった。「すごい指導ができると思っていなくて、調整や人をまとめることをやっています」
監督が他の指導者を信頼し、一部選手の育成を任せるやり方は昨今の実業団チームで増えている。その一方で練習の設定タイムや区間配置など、伊藤監督は自身の考え方も出している。そういったバランスの良さや、細かい判断が総合されたものが今回の初優勝につながった。学生時代に活躍した選手たちと、地道に経験を積み重ねてきた指導者の組み合わせが、GMOに新たな力を呼び起こしている。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)
*写真は7区を走った小野知大選手