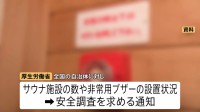“日本らしさ”はいかにして作られたのか? 「日本スゴい!」の裏にある空虚を考える

私たちは「日本文化」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。富士山、相撲、アニメ……。しかし、これらのイメージはどのように「日本らしさ」として定着したのでしょうか。
戦前の写真、映画、雑誌、紙芝居といったメディアを分析し、「モンタージュ」という概念から日本文化論の成立を読み解いてきた研究者の大塚英志さん(国際日本文化研究センター名誉教授)に、「日本文化論はどうつくられてきたか」を伺いました。
(TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月24日放送「『日本文化論』はどう創られてきたか?」より。構成:菅谷優駿)
「オタク第一世代」として始まった文化研究の道
大塚英志さんは「オタク第一世代」を自認し、「自分が好きな表現の源流は何か」という問いから研究を始めたと語ります。
「例えば漫画の『映画的手法』って一体何なんだろうと考え始めると、遡っていくといつの間にか戦前に行き着く。多くの表現が戦前に行くんですよ。そこから見えてくる自分の表現の見取り図に夢中になって、過去へ過去へと遡っていった」
大塚さんは漫画家を目指していましたが、「才能がなかった」として、漫画雑誌の編集者、そして原作者へと転身。「オタクであることと、オタクであることの系譜みたいなことをずっと、作る側と系譜を探るみたいなことを極めて個人的な動機でやってきた」と話します。
「戦時下の大衆文化研究とアカデミックに言えばもっともらしくなるんですけど、実際は手塚治虫の方法を遡ったら戦時下に行くし、特撮の系譜を遡っていったら戦時下の映画表現に行く」
「モンタージュ」とは何か?
大塚さんが日本文化論を読み解く上で注目したのが「モンタージュ」という概念です。モンタージュとは、もともと映画用語で、ソビエト映画監督エイゼンシュテインらが理論化した手法です。
「1つの場面を1カットと考え、カットとカットをつなぐことが編集。その『つなぐ』と別の意味が生まれてくる。カットAとカットBを結びつけると、A+Bじゃなくて、それを超越するような新しい意味Cが生まれてくる」
例えば、人が俯いている映像の後に、ベッドに横たわる女性の映像をつなげれば性的な妄想をしているように見え、料理の映像をつなげれば空腹を表現していることになる。同じ表情でも、つなげるものによって意味が変わっていくのです。
大塚さんは「それはもうプロパガンダのための映像理論」と指摘します。同時に、「グラフ・モンタージュ」という写真を切り貼りしていく手法もあり、これら二種類のモンタージュが戦時中の日本で重なり合っていたと説明します。
「日本文化=モンタージュ」という誤解の始まり
エイゼンシュテインは「日本文化をモンタージュとして論じる」という文章を書いており、それが翻訳されて日本に入ってきました。この中で漢字、俳句、能や歌舞伎の演技などが「モンタージュ的」と論じられています。
「例えば漢字は『偏(へん)』と『旁(つくり)』があります。『さんずい』は水の象形文字ですよね。たとえば涙を意味する『泪』という字は、『さんずい』という象形文字と『目』という象形文字をモンタージュすると涙になる。歌舞伎や能の動作も、手だけ先に動かして、次に右手が動き、その後にゆっくりと左手が動いて……と動作が分断されて連続する。これもモンタージュだ」と。
しかし、エイゼンシュテインの結論は「日本映画はモンタージュではない」というものでした。これは、ソビエト社会主義陣営の理論家として、「日本文化をモンタージュだと賛美しておきながら、しかしお前たちはまだモンタージュを知らない。我々の陣営に来い」という政治的意図があったと大塚さんは分析します。
「外国人から褒められると喜んじゃうという悪い癖があるわけです。『我々はそうだったのか』と思っちゃって。この翻訳が出た後に日本文化モンタージュ説が1つの社会現象になった」
日本文化論の転倒—解釈が本質にすり替わる
この日本文化モンタージュ説は、昭和10年頃に広く流布していきました。そして奇妙な転倒が起きます。「日本文化がモンタージュ的」というより、「日本文化の一部、特に近代メディアや新しい表現をモンタージュ化していく」という現象が起きたのです。
例えば、「絵巻物はモンタージュだ」という主張が美術評論家や技術評論家から出てきます。しかし、これは「モンタージュのように絵巻物を見る」ことであって、「絵巻物がモンタージュ」なのではありません。解釈のひとつに過ぎなかったものが、本質だと言われるようになったのです。
「日本文化=絵巻物=モンタージュ的みたいな風に意味がスライドしていく。日本文化論がモンタージュ論と同義になり、モンタージュ論に飲み込まれていく」
モンタージュ化する日本の表現—紙芝居の近代的発明
モンタージュ理論が日本文化の解釈に影響を与えただけでなく、実際の表現方法にも影響を与えました。その象徴的な例が「紙芝居」です。
「紙芝居は下町情緒的なもので、どこか日本の伝統的な文化だと思われていますが、江戸時代に紙芝居はありませんでした。時代劇で紙芝居が出てくるシーンがないはずです」
現在の紙芝居の原型は昭和初期に生まれたもので、加太こうじという人物が「モンタージュ論」を取り入れて改革したといいます。加太こうじは紙芝居業界の人物でしたが、当時モンタージュという概念が広く浸透していたことを示しています。
「彼はアップやロングショットなど、映画的な手法を取り入れて紙芝居を革新しました。そして日中戦争を経てアジア太平洋戦争が始まると、紙芝居はプロパガンダのツールとして一気に使われるようになる」
戦時下のプロパガンダと戦後の広告産業
戦時中、モンタージュ技法は映画でも活用されました。特にドキュメンタリー映画(当時は「文化映画」と呼ばれた)でモンタージュが多用されます。これらは映画法によって事実上の強制上映となり、戦争記録映画から科学啓蒙映画まで様々なプロパガンダ映画が作られました。
「かつて左翼思想の映画運動に参加していた映画人たちが、戦時中に転向してそういった映画に手を染めていく。彼らはソビエトのモンタージュ論的な映画の作法を使いながら、日本のプロパガンダ映画を作っていった」
興味深いのは、これらの表現手法や人材が戦後も生き延び、広告産業に流れていったことです。
「戦時中のプロパガンダに関わった人たちが戦後に生き延びていきながら、戦後のメディア産業をかたちづくっていった。クライアントが変わっただけで、方法論自体は変わっていない。広告というのは元々プロパガンダなんです」
「日本すごい」の空虚さ—実体のない文化イメージ
戦前の万国博覧会で日本館が展示したのは、富士山、芸者、仏像といったステレオタイプな日本のイメージをモンタージュした巨大な写真壁画でした。そこには「何を発信するか」という内実がありません。
「ナチスドイツやソビエトの万博パビリオンは強烈なプロパガンダなのに、日本はのほほんとした『芸者・富士山』みたいなことを発信していた」
大塚さんはこれを「パブリックイメージ以前の日本」と呼び、現代のプロジェクションマッピングなどにも同じ問題を見ています。
「わけもわからずゴジラを出してみるとか。ゴジラがどういう風に日本の表象なのかと考えもせず、とりあえず並べておいたらなんとなく日本らしくなるだろう、と納得してしまう水準で日本が語られ、作られていく」
庵野秀明と戦時下アヴァンギャルドの系譜
大塚さんは、現代の表現者たちの中にも戦時下のモンタージュ的表現の影響を見出します。特に映画監督の庵野秀明さんについて興味深い分析を示しました。
「『新世紀エヴァンゲリオン』の最後のポスターがエッフェル塔をローアングルで撮っているでしょう? あれは1920年代のパリで撮られた前衛写真が元ネタなんです。知っている人が見れば『ああ』とネタばらしになっている」
庵野秀明さんの撮影スタイルについても言及します。
「庵野氏が写真を撮る姿を奥さんや娘さんが撮った写真があります。彼はどこに行っても地面に這いつくばったり、ひっくり返ったりして、下から撮っている。そうやって地べたにはいつくばり、あらゆる角度の写真を撮るというのは、ジガ・ヴェルトフというソビエトの映画監督がやっていたことなんです」
このような表現の系譜をたどると、戦時下のアヴァンギャルドを経由して、戦後のオタク文化に届いていることがわかります。
「僕らがオタクとして好きな表現を遡っていくと、戦時中に行き着く。特撮がたまらないと思っていたら、ゴジラの東宝特撮を経由して戦時中の特殊撮影に行く。そこで特撮がどう使われていたかというと、『リアルな戦闘シーン』を再現するため、つまり文化映画的な戦闘シーンを再現するためだったんです」
現代に続く「日本らしさ」の空虚な語り
大塚さんの指摘する問題は現代にも続いています。「日本文化」という言葉が検証されないまま使われ、「日本らしくない」という否定によってのみ「日本らしさ」が浮かび上がる構図は今も変わりません。
「モンタージュ的な手法は現代でも情報を操作する手法として生きている。『切り取り』という言葉自体がモンタージュで、自分の意に沿うモンタージュならいいけれど、意に反するモンタージュをされたら怒る」
日本文化について語るとき、私たちはしばしば「日本的」というだけで、日本が何かという議論をしていません。「日本らしさ」とは、結局のところ、様々なイメージの断片をモンタージュして作られた虚構なのかもしれません。それを自覚することが、文化を語る上での第一歩ではないでしょうか。
(TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月24日放送「『日本文化論』はどう創られてきたか?」より)